この記事を読んで欲しい人 | 特例認定 | 取得方法
この記事は
- 防火対象物点検、防災管理点検の費用がもったいない!
- 特定認定を取得したい。経費を少しでも削減したい!
- 防火対象物点検、防災管理点検を3年間クリアした!
上記の方向けに書いています。
もくじ | 特例認定 | 取得方法
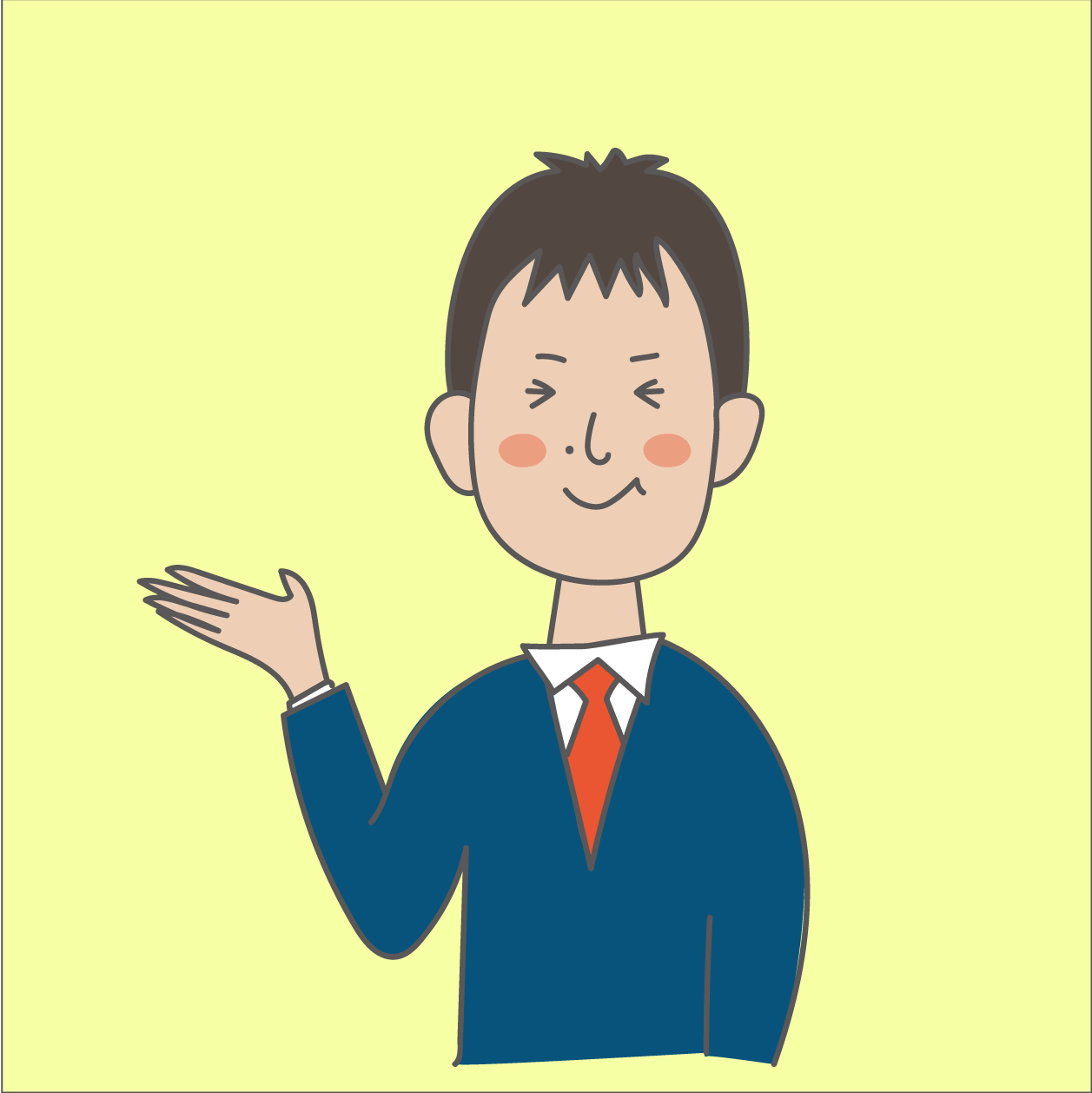
今回は複数の企業が入居しているビルの入居者側の手続きを想定してまとめました。
特例認定とは | 特例認定 | 取得方法

特例認定とは、優良の防火対象物として消防署から認定をうけることで、認定を得てから3年間、防火対象物点検・防災管理点検の実施と報告が免除される制度のことです。
東京消防庁HP
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/tenken/tenk-toku.htm

「防火・防災優良認定証」の表記を見たことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。
取得のメリットは | 特例認定 | 取得方法
特例認定を取得することで
- 防火防災優良認定証の交付を受けられる(ビル全体で取得した場合)
- 防火対象物点検、防災管理点検が不要になる

点検費用分の経費削減と、毎年消防署へ提出にいく手間が省けるのが大きいと思います。
申請の流れ | 特例認定 | 取得方法

ここからは、具体的に特例認定の申請の流れについて説明して行きます。

申請は「書類審査」「現地確認」の順に行います!順に説明して行きます。
書類審査 | 特例認定 | 取得方法
まずは書類審査です。管轄の消防署へ電話でアポイントをとり、書類を一式持って行きます。持っていく内容としては、
- 消防計画
- 自主検査チェック表(3年分)
- 防火防災管理者選任届出
- 防火対象物理点検、防災管理点検報告書(3年分、消防署への届出済みのもの)
- 防災訓練結果通知書(3年分)
- ビルとの契約書
これらを持参して、消防署でチェックをもらいます。上記だけで足りない可能性もありますので消防署へのアポイントの際に必要なものを確認してから伺うといいでしょう。

消防署の担当官によって指摘してくることが少し異なるケースもあります。何を言われるか分からないという心の準備をしておくことも必要です。
書類審査で問題がなければ、次の現地確認の日程を決めます。
現地確認 | 特例認定 | 取得方法
書類確認を無事にクリアするとそのあとは現地確認です。現地で確認する項目としては、
- 消防書類が適切に保管されているか
- 避難通路、避難設備が適切に管理されているか
- 什器に転倒防止措置がきちんとされているか
などがチェック項目です。現地確認においても、担当官次第で若干異なるので注意してください。

書類と現地確認をクリアすれば晴れて特例認定です!3年間有効で、3年以内にまた同様の手続き行えば、再度3年間受けることができます。
次に、特例認定前の具体的な準備に関してまとめて行きます。
申請前に確認すること | 特例認定 | 取得方法

ここからは、申請手続きに入る前に必要な手続きを順にまとめて行きます。一つ一つチェックして、問題がなければ、申請の手続きに入りましょう。
防火対象物点検・防災管理点検の3年間継続しての実施 | 特例認定 | 取得方法
まずは防火対象物点検、防災管理点検に関しての確認です。
- 3年間継続して実施
- 消防署への届出をきちんと行なっている
- 点検結果も問題がなく、全ての項目に「適」にチェックが入っている
この条件を満たすことが必要です。
継続する3年間の数え方ですが、ビルとの契約を開始した月を起点とする1年間を事業年度と数えます。
事業年度ごとに1度実施すれば良いので、必ず同じ月に実施しなければいけない訳ではありません。
申請が可能かどうか、詳しくは消防署へお問い合わせください。
防火防災管理者の有効期限確認 | 特例認定 | 取得方法
防火防災管理者証には5年間の有効期限があります。切れていないか確認しましょう。
切れている場合は、再講習の受講が必要です。
講習時間 9:00〜12:30
受講費用 1300円(テキスト代)
東京消防庁HP
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/sk/kousyu05.html
新規講習と比べると、講習の日程が少ないので早めに調べておきましょう。

運転免許証とは違い、更新のお知らせは来ませんので、自分で確認が必要です。
自主検査チェック表の確認 | 特例認定 | 取得方法
入居時に作成・提出した消防計画の中に、
- 自主検査チェック表(日常)
- 自主検査チェク表(定期)
が含まれていると思います。その計画通りにきちんと記録が残されているかを確認します。
- については、毎日の最終退館社が戸締りや可燃物放置などを確認する
- については、おおよそ年に2回程度
となっていることが多いと思います。

消防計画の条文は、各企業ごとに異なります。まずは提出済みの消防計画を見直して、きちんと計画通りに実施されているかを確認しましょう。
(もし記録がない場合、自主検査チェック表は遡って書いても・・・)
防災訓練記録の確認 | 特例認定 | 取得方法
消防法で、年に2回の防災訓練が義務付けられています。訓練の際には
- 訓練の前に「訓練通知書」
- 訓練後に消防訓練実施計画報告書
の作成、保管が必要になっています。ビルに入居している場合はビル側がまとめて実施していることが多いのでビル側に書面をもらっておきましょう。

日頃から、ビルで実施する防災訓練に参加していることが必要ですよ!
消防計画の確認 | 特例認定 | 取得方法
消防計画に変更があれば、最新の状態にしておく必要があります。主なものとしては、
- 自衛消防隊の変更
- 帰宅困難時の時差退社計画
- 備蓄品の個数
- 備蓄品の賞味期限が切れていないか

人事異動や新規採用、退職の際にありがちです。再度見直しましょう。
転倒防止措置 | 特例認定 | 取得方法
現地確認時のチェック項目についても準備しておきましょう。背の高い什器に関しては個別に対処が必要です。具体的には、
- キャビネットに入っている書類が飛び出さないように(扉が締まればOK)
- 什器本体を固定して転倒防止措置
これらの対処が必要です。
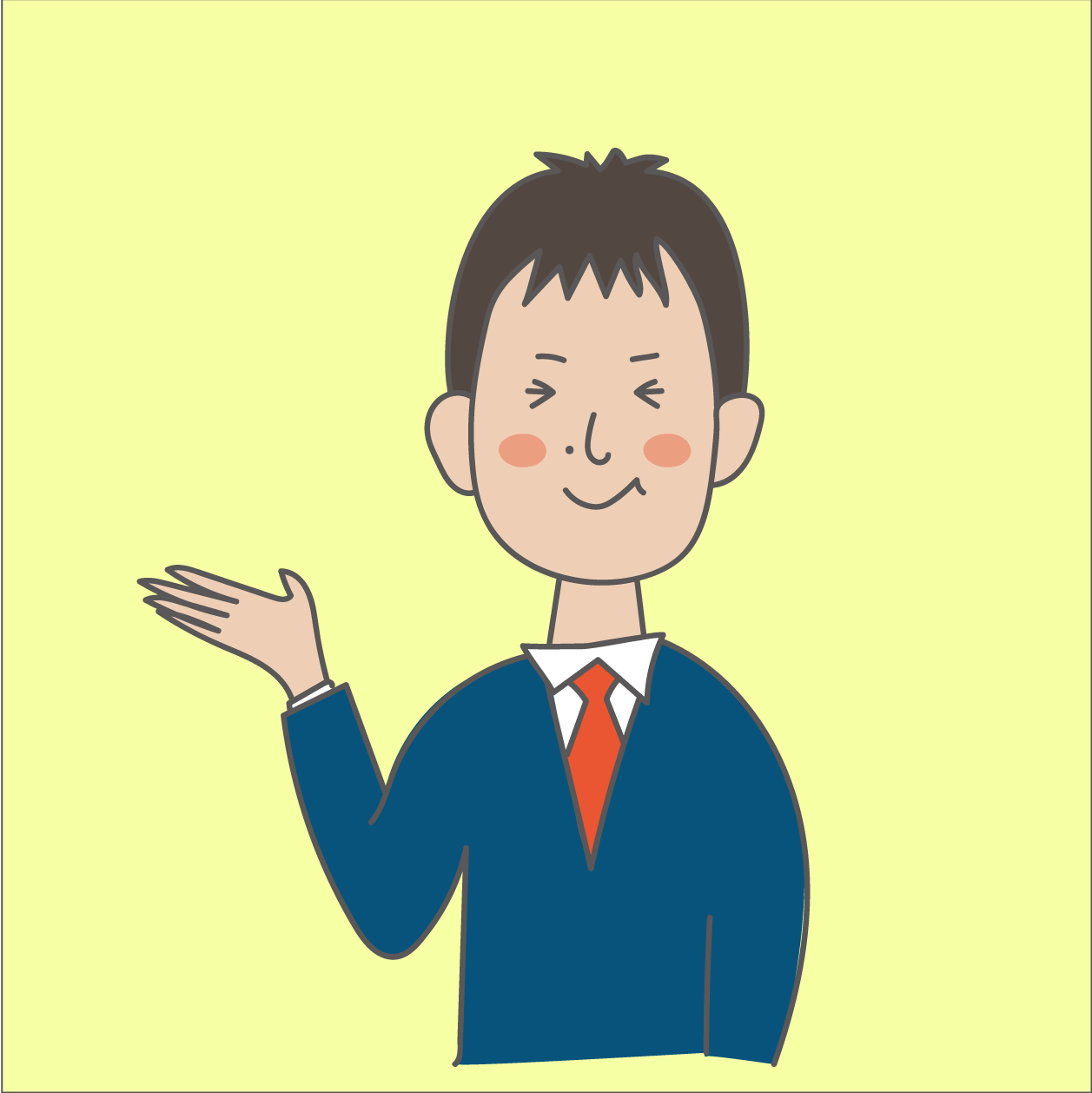
ビルに入居している場合、固定する中で壁などに穴を開けないようにする必要があると思います。天井面への突っ張り棒や、下にクサビを入れるなどの配慮は必要です。
内装の防炎認定 | 特例認定 | 取得方法
専有部内の内装について、防炎認定を受けた内装材である必要があります。
- 床のタイルカーペット
- カーテン
- ブラインド
- 布製のパーテーション

「防炎」のマークがある事を確認しましょう。もし見つからない場合は、内装を行なった業者さんに言ってつけてもらいまいます。
ブラインドについて、ビル側設備の場合は確認が必要です。
終わりに | 特例認定 | 取得方法
消防からのお墨付きである特例認定。経費の削減になりますし、何より防災対策をしっかりやった結果です。
防火防災体制を整えておくことは、万が一の災害の時にも非常に有効です。この機会にぜひ一度確認することをお勧めします。

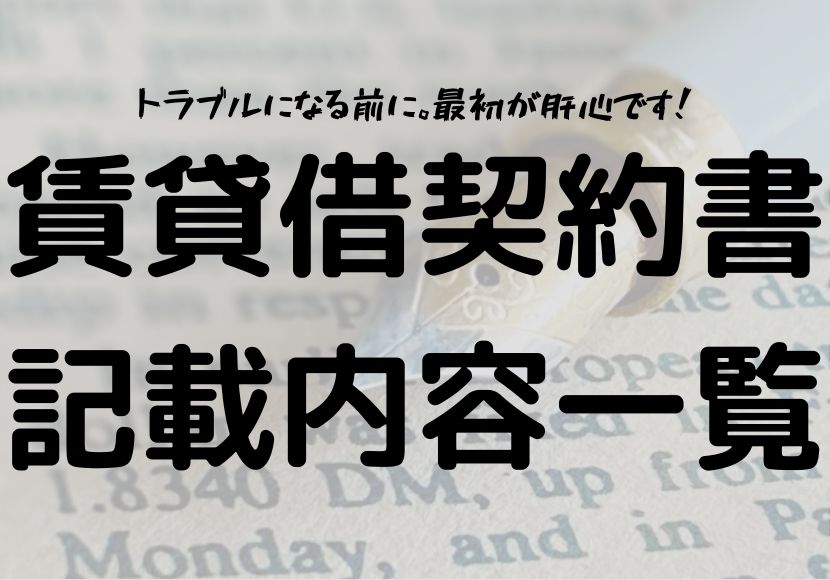
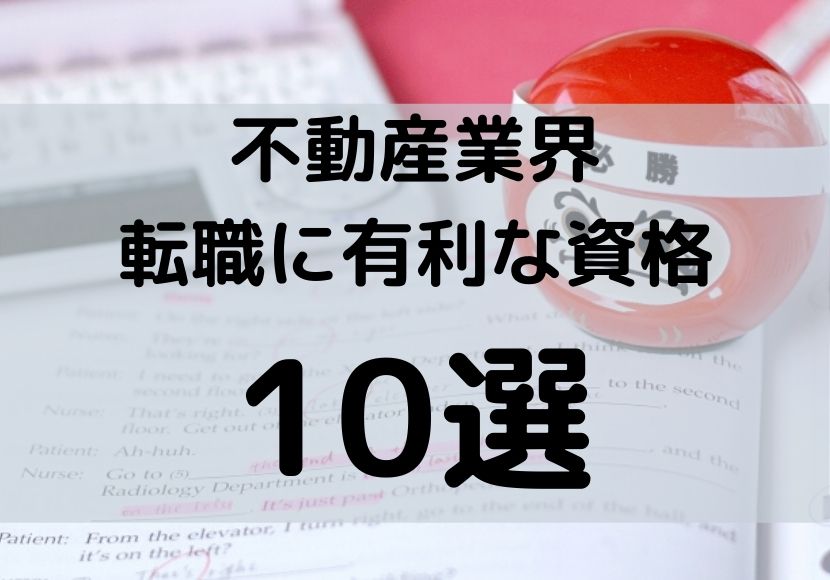
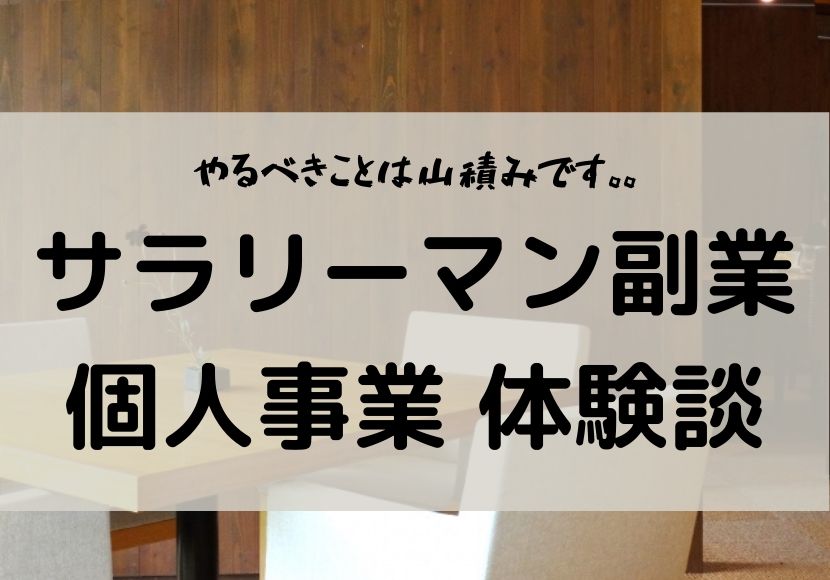
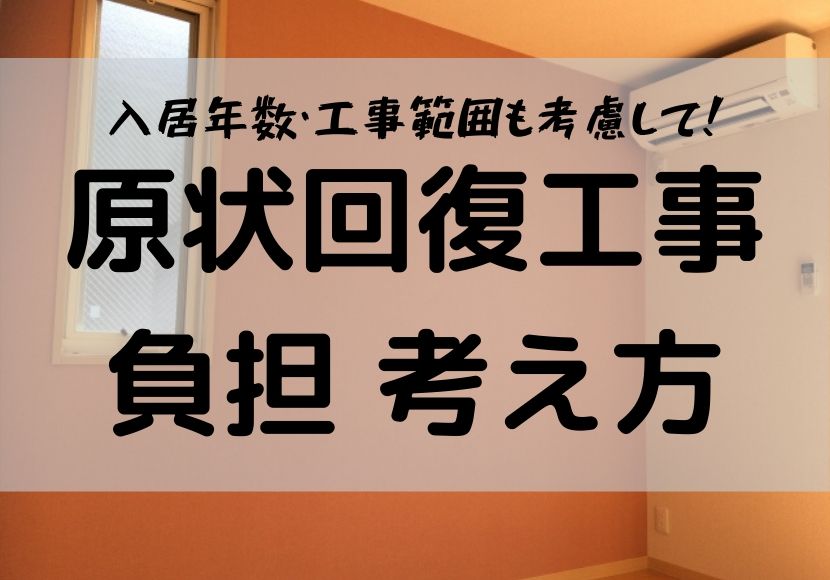
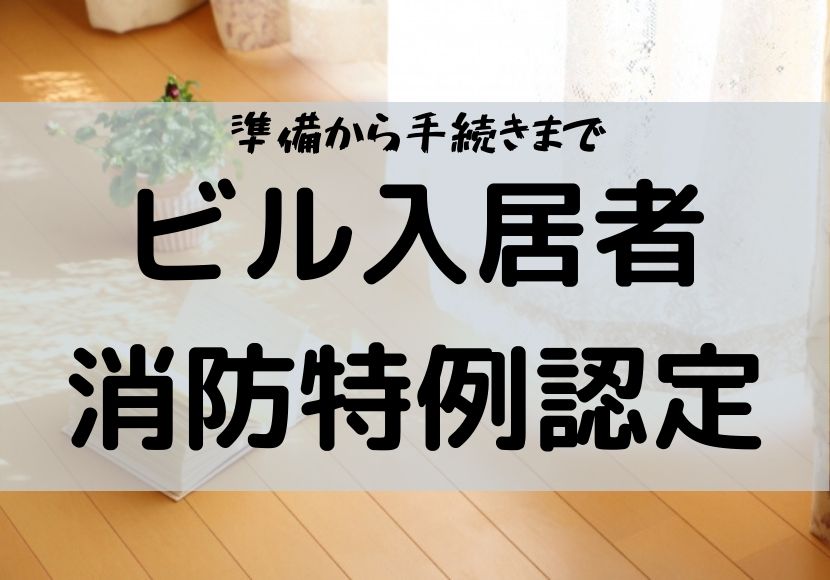



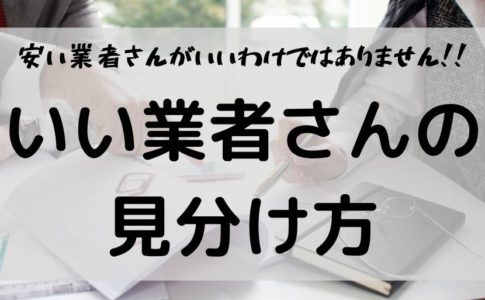


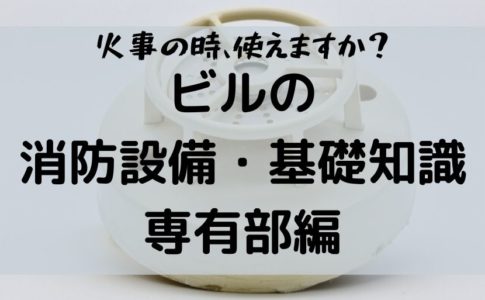

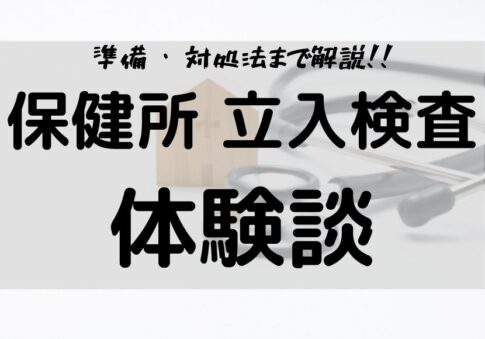
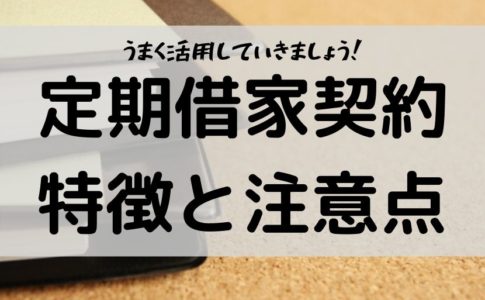
大規模ビルで消防の特例認定を取得する場合の手続きについてまとめました。
一度手続きをすると3年間の点検、報告が免除されます。