この記事を読んで欲しい人 | 定期借家契約 | 特徴 | 注意点
この記事を読むことで、
- 定期借家契約ってなに?
- オーナー側から定期借家契約を提示されたけど、不利になったりするの?
- 定期借家契約の実務上の注意点は?
という疑問が解決できます。
もくじ | 定期借家契約 | 特徴 | 注意点

私はビルオーナー側の担当者としてテナントさんとの契約の時によく定期借家契約で締結しています。実務上注意すべき点を重点的にまとめました。
定期借家契約とは | 定期借家契約 | 特徴 | 注意点
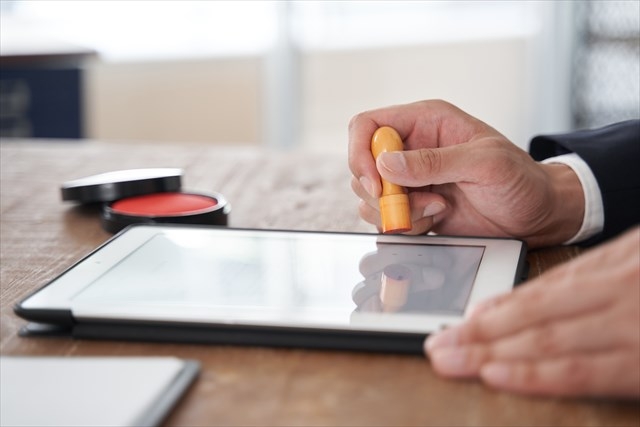
その名前のとおり、一番の特徴は定期(=更新がない)ことです。
本来、借地借家法では賃貸人(=オーナーさん)側からの解約には正当事由が必要であり、一度契約してしまうとなかなか解約ができない事が後々のトラブルの原因になったりします。
その点、定期借家契約で契約する事で、契約で合意した期間の満了とともに契約を終了させる事ができるのです。
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。
借地借家法第38条1項
普通借家契約との違い | 定期借家契約 | 特徴 | 注意点
普通借家契約との違いを要約すると、つぎのとおりです。
| 定期借家契約 | 普通借家契約 | |
| 契約の方法 | 公正証書等の書面による必要がある | 口頭でも可 |
| 契約期間 | 1年未満でも可 | 1年以上 |
| 更新 | 更新なし | 正当事由がない限り更新 |
| 賃料の減額請求 | 特約で排除できる | 排除できない |

項目ごとに説明していきます!
契約の方法 | 定期借家契約 | 特徴 | 注意点
民法の規定によると、普通借家契約については口頭での契約も有効です。(通常はそのようなリスクの高いことはしないと思いますが)
一方、定期借家契約は
- 契約は、公正証等の書面によらなければならない
- 契約が期間満了で終了することを説明しなければならない
- 「あらかじめ」「書面を交付して」説明すること
という規定があります。
前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
借地借家法38条2項

❷は事前に、適切にされなければ無効です。後ほど詳しく説明します。
契約期間 | 定期借家契約 | 特徴 | 注意点

普通賃貸借契約において、1年未満の期間で契約してもその部分は無効となり、期間の定めのない賃貸借と見なされます。その場合は、解約申し入れの日から3ヶ月後に解約となります。(ただし、賃貸人(=オーナーさん)からの解約には正当事由が必要。)
一方、定期借家契約においては1年未満でも可能となっています。
契約の更新 | 定期借家契約 | 特徴 | 注意点
普通借家契約においては、賃貸人(=オーナーさん)から契約を終了させたくても正当事由がなければ解約する事ができません。
建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
借地借家法第28条
一方、定期借家契約は期間満了により契約終了となります。
ただし、賃貸人(=オーナー)から、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に賃借人に対し、終了する旨の通知をしなければなりません。
反対に継続したい場合も「更新」は存在しないため、賃貸人(=オーナー)と賃借人(=入居者)で協議の上「再契約」をすることになります。

建て替え直前のビルなどで、立ち退き費用などの折り合いがつかずに居座っているのをたまに見ますが、そういうトラブルを防ぐために定期借家契約が有効です。
賃料の減額請求 | 定期借家契約 | 特徴 | 注意点
普通借家契約においては、「契約期間中の賃料の減額請求を行わない」といった特約を設けても無効です。
一方で、定期借家契約においては特約により「賃料の減額請求を行わない」といった旨の合意も有効です。

不動産における契約は基本的に賃借人(=入居者)に有利になっています。
注意点 | 定期借家契約 | 特徴 | 注意点
賃貸人(=オーナー)側にとってメリットの多い定期借家契約ですが、締結するにあたり注意する点も多々あります。順に説明していきます。
事前説明書の締結 | 定期借家契約 | 特徴 | 注意点

先に少し触れましたが、契約締結前に「あらかじめ」書面を交付して、定期借家契約であることを説明しなければなりません。
書面には、
- 契約の更新ができないこと
- 期間満了にて終了すること
などを記載して、賃貸人(=オーナー)から(賃借人=入居者)へ交付し、交付され内容を確認した旨とその日付を賃借人が記入してもらう形をとると安心だと思います。

事前説明書類は、契約書とは別の書面である事が必要です。また、実務でよくあるのが、賃借人からの説明を確認した日付の記入を忘れてしまう事です。
事前説明書類に不備があった場合は、普通賃貸借契約として扱われることがあります。
期間満了前の書面 | 定期借家契約 | 特徴 | 注意点
先に少し触れましたが、賃貸人(=オーナー)から、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に賃借人に対し、終了する旨の通知をする事で、期間の満了に伴って終了する事ができます。
逆に言えば、定期借家契約といえど、この通知を忘れてしまうと終了する事ができませんので注意が必要です。

万が一、書面での通知を忘れてしまい期間が過ぎてしまった場合、通知した日から6ヶ月経過後に契約が終了する事になります。
ただし、賃貸借期間が1年未満の定期借家契約では終了通知は不要です。双方が当然憶えていると考えられるためです。
賃料は割安傾向 | 定期借家契約 | 特徴 | 注意点

定期借家契約と普通借家契約とで比較してきましたが、一般的に賃料は割安になリます。賃借人(=入居者)側の立場で考えてみると分かりやすいのですが、
- 契約の更新が出来ないので、長く入居できない可能性がある
- 賃料の減額に応じてもらえない可能性がある
- 再契約の交渉の時に賃料を増額される可能性もある
このように賃借人の立場から考えると、せっかく引っ越しや内装工事費用をかけて入居したので長く入居したいと考えても、いつまでいることができるかわからないビルであれば入居しにくい側面もあるので賃料は下がります。
まとめ | 定期借家契約 | 特徴 | 注意点
ビルのオーナー側が定期借家契約を選択する大きな理由として
- ビルの建て替えが目に見えているので、その時期にビル全体を空室にしたい
- ビルにとっては飲食店は顔。定期的に入れ替えて飽きないようにしたい
など、ビル経営の戦略上の理由が挙げられます。
ここで紹介したように必要な事務処理の量は増えますが、将来の建て替えなどを計画し、もっともっと定期借家契約がもっと一般的に広まればいいのにと思っています。
実務上の注意点などをりっかり理解した上で扱っていきたいですね。

テナント数が多かったり、ビル経営担当者が少ない場合は、解約通知の期日管理などが大変になることもあります。ひながたの作成等、請け負うことも可能です。お問い合わせくださいね。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!

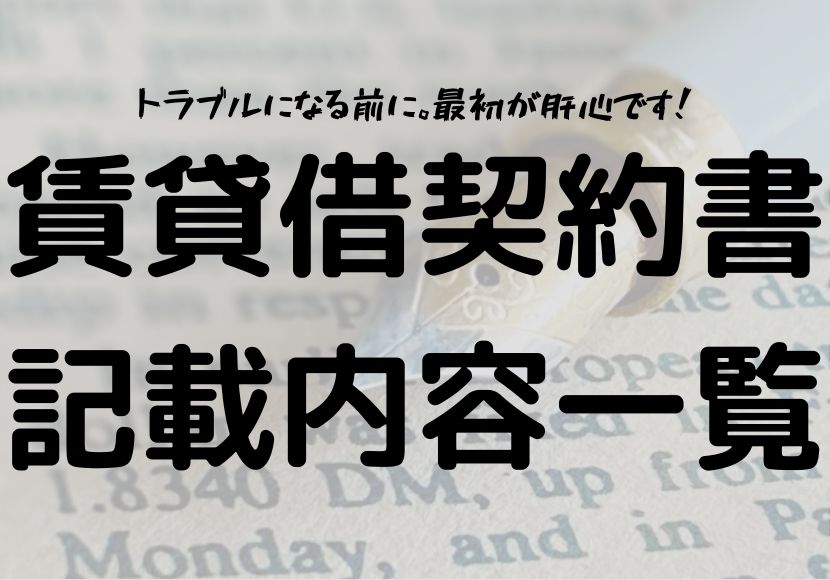
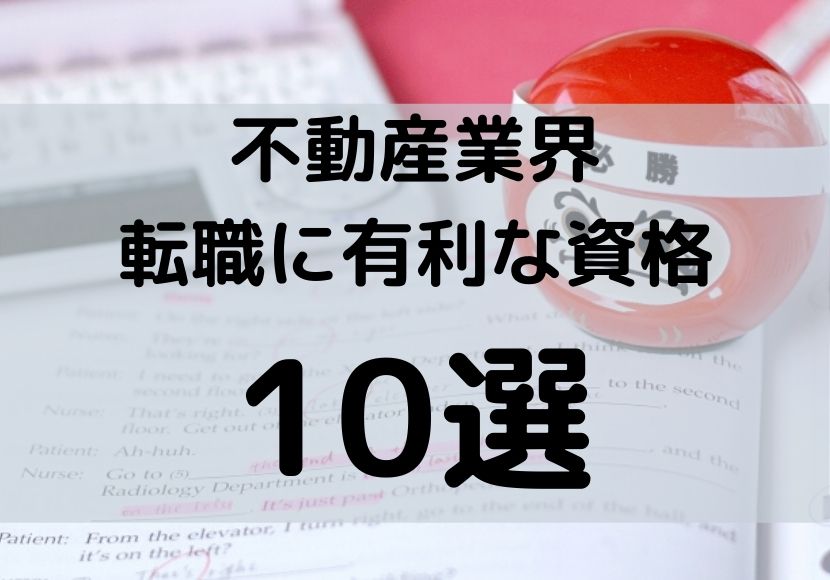
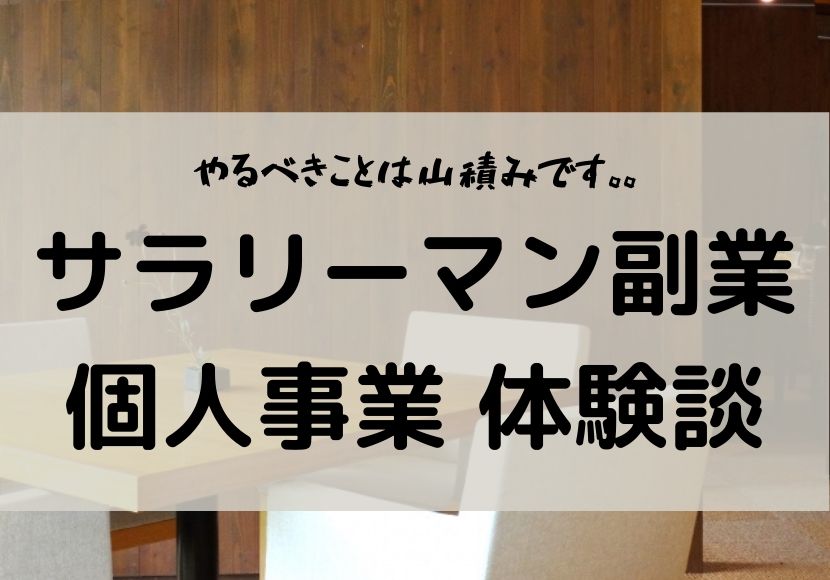
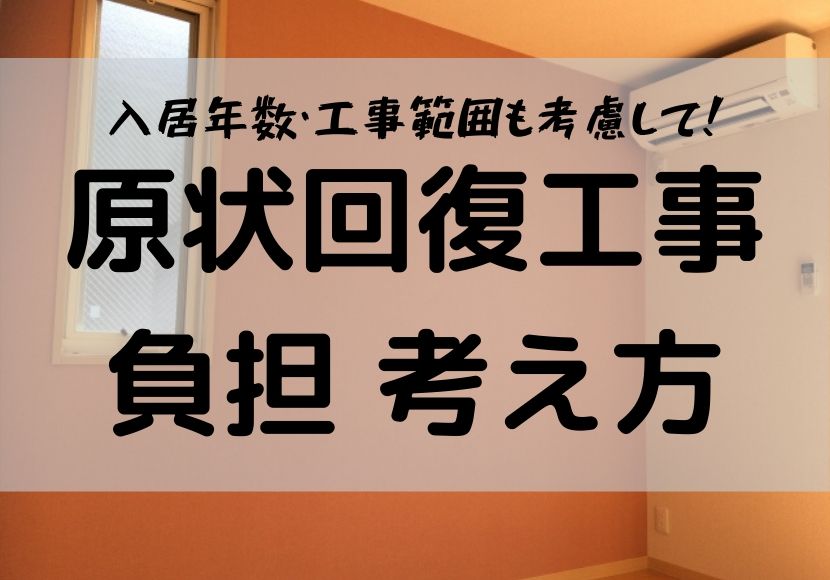
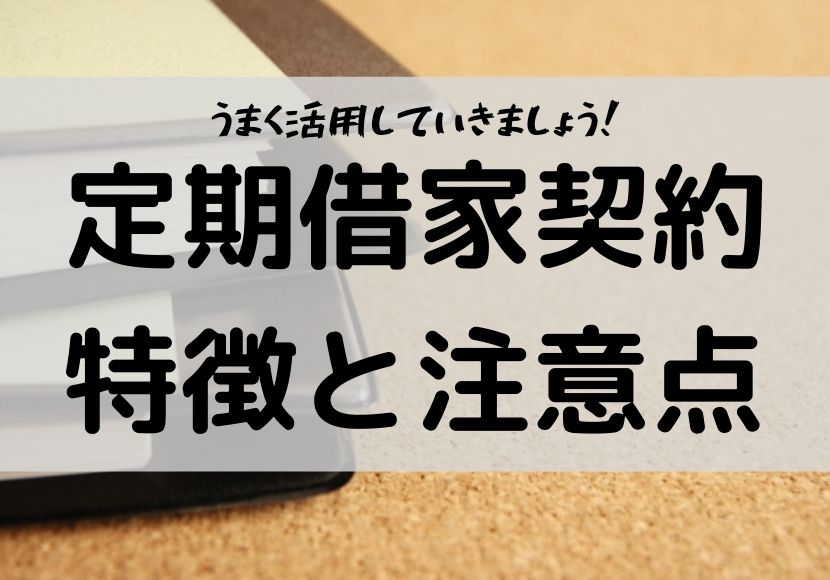



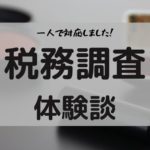
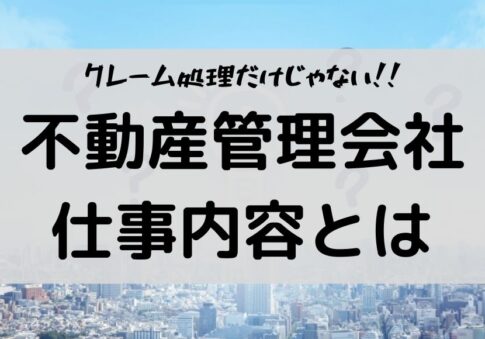

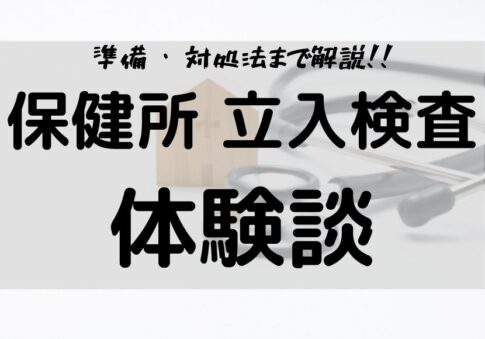


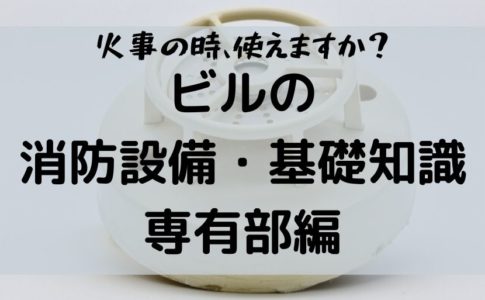
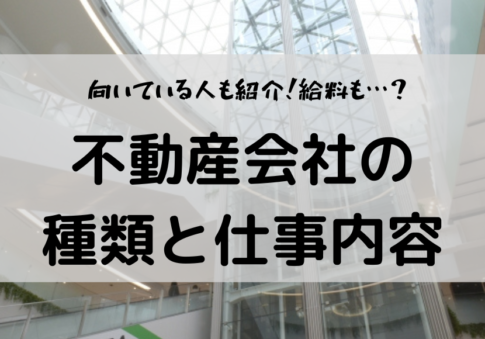
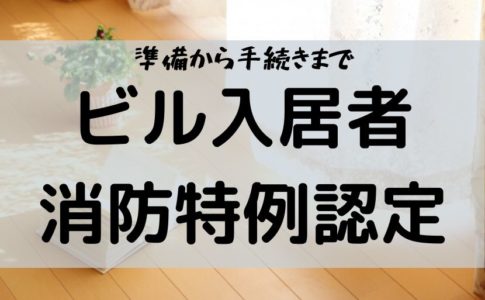
事業用でも居住用でも、注意点は同じです。